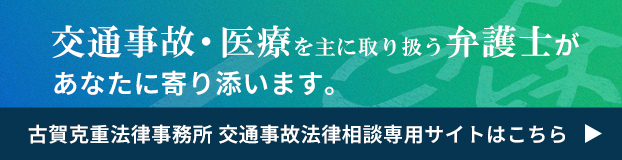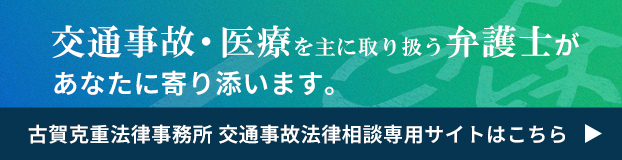解説
【事案の概要】
X(20代男性)は、2月17日午後8時頃から翌日の午前10時頃までの間、公園の駐車場に被保険車両の外国製高級乗用車を駐車していたところ、車体全体にわたって多数の傷を付けられ、車内に消火剤を散布され全損になったとして、自動車保険契約を締結する損保に対し、車両保険金等710万円を求めて訴えを提起しました。
一審裁判所は、本件事故がXの故意により生じた事故であると認めるには足りないとして、Xの保険金請求を認容しました。
損保が控訴した二審裁判所は、一審判決を取り消し、本件事故はXの故意により生じたと認定し、保険金請求を棄却しました(確定。自保ジャーナル2178号138頁)。
【裁判所の判断】
一審において、被告は、本件車両の多数の損傷は、一定の重量があり先端が尖った金属製の凶器によるものであること、本件駐車場に消火器は設置されていないこと、本件駐車場は暗闇の通路を何百メートルも走行した先にあること、原告が本件車両を駐車した場所は、本件駐車場の出入口から65mも入り込んだ場所であることなどから、通りすがりの第三者が本件事故を生じさせたとは考え難い旨を主張しました。
これに対して、一審裁判所は、本件車両の車体の多数の損傷中には、一定の重量があり先端が尖った金属製の道具(先端の尖ったハンマーのような道具)によって付けられたと考えられる損傷があるところ、このことは、本件駐車場付近で容易に入手できる石や木片、あるいは、通常携帯される鍵やコイン等によって車体への損傷行為が行われる場合と比較すれば、本件事故が特異な形態の損傷行為であるということはできるが、第三者による損傷行為であることが合理的に排除される事情であるとまではいえない。他方、原告がそのような道具を所持していたことをうかがわせる事情や、原告であればそのような道具を使用する可能性が高いといえるような事情も見当たらない。消火器が使用されたことについても同様に、第三者による損傷行為であることが合理的に排除される事情であるとまではいえない。本件駐車場は、公園内の駐車場であり、夜間に車両や人の通行が少ない場所であることは認められるが、原告以外に訪れる者がいることは考えにくいとはいえない、と指摘しました。
また、被告は、本件車両の左後ろの窓だけが2~3cm開いており、そこから消火剤が噴射されているところ、本件車両の左後ろは、公園の通路からみて死角となる場所であり、また、たまたま左後ろだけ閉め忘れたというのは極めて不自然であると主張しました。
これに対して一審裁判所は、本件車両の左後ろの窓が2~3cm空いていたことについて、原告は、本件車両を運転中にたばこを吸う際には、車内がやにっぽくならないように、いつも4つの窓全部を開けるようにしており、本件事故前(2月17日)にも、運転中の4つのボタンを操作して4つの窓を開けてたばこを吸い、吸い終わった後、運転しながら4つのボタンを操作して窓を全部閉めたつもりであったが、左後ろの窓だけ閉め切れていなかったのかもしれない旨を説明、供述しているところ、これが信用できないことを根拠付ける事情は見当たらないと指摘しました。
さらに、被告は、原告は1月の転職を機に本件車両の使用頻度が落ち、本件事故当時本件車両は原告にとって不要な車であったこと及び本件事故当時、原告は、本件車両について毎月8万5800円のローンを支払っていてその残債務額は約568万円であり、本件車両を売却しても390万円程度にしかならないため、本件事故を作出して710万円の保険金が支払われると、原告は約142万円を得ることができるから、原告には、本件事故を作出する動機があったと主張しました。
これに対して一審裁判所は、原告が、本件事故当時、本件車両が不要になっていたと認めるに足りる証拠はなく、かえって、原告は、被告の指摘する転職の前後を通じて、中距離・長距離のトラック運転手であり、生活状況に特に変化がなかったと認められる。また、本件車両は、原告が、当時乗っていたアウディ(下取り価格350万円)から乗り換えとして購入した車両であり、分割払手数料込みで約620万円のローンを組んでいたところ、本件事故時までに支払いの遅滞はなかったこと及び原告は、外車が好きで、BMW、アウディ、本件車両の順に、2~3年ごとに乗り換えてきたことが認められ、他方、本件事故までに、原告が本件車両が不要になったことをうかがわせる事情は見当たらない。また原告は、トラック運転手として稼働し、その給与所得(支払金額)は、事故前年が約550万円、事故当年が約720万円であり、この他に、父から相続した賃貸物件の家賃収入が年間約90万円余あること、独身で実家に居住していたこと及び原告に本件車両ローン以外に負債があるとは認められないことからすると、原告が、保険事故を偽装して保険金を詐取することを欲するような経済状況にあったとは言うことはできないとして、原告に本件事故を故意に生じさせる動機があるとは認めることはできないと指摘しました。
こうして一審裁判所は、本件事故が原告の故意により生じた事故であると認めるには足りないと判断しました。
これに対して、二審である大阪高等裁判所は、被控訴人は、本件事故の経緯につき、2月17日に兄が自分の車両に乗って被控訴人宅を訪れ、ガレージに同車両を駐車したので、被控訴人は、一時的に本件車両を道路上に停めたが、兄が、飲酒し、運転して帰ることができなくなったため、被控訴人は、本件車両を道路上に放置しておくと近所迷惑となると考えて、本件車両を本件駐車場に駐車しに行った、そして、翌朝、被控訴人が本件車両を取りに行ったところ、本件車両外部に多数の傷が付けられ、車室内に消火剤が散布されていることを発見したと主張するが、兄が2月17日に被控訴人宅を訪れたことは、本件事故の経緯に係る被控訴人の主張及び供述の根幹となる前提事実であるところ、兄がトラック運転手として当時運転していたトラックのETC走行履歴によれば、同トラックは、2月17日午後8時19分c入口を利用し、同月18日午前8時59分にd出口を利用しているのであるから、被控訴人がそもそもの前提とする兄が同月17日に被控訴人宅を訪れたという事実は認められないというほかないと指摘しました。
また、兄が被控訴人宅を訪れた事実が認められない以上、車両をガレージに停めた兄が飲酒し運転できなくなったので、近所迷惑にならないよう路上に駐車していた本件車両を本件駐車場に駐車しに行ったとの被控訴人の説明は全く成り立たず、被控訴人は、同月18日午前3時頃という深夜の時間帯に、人気の少ない本件駐車場に本件車両を敢えて移動させたことにつき、何ら合理的な説明をしていないこととなるし、被控訴人が一貫して兄が被控訴人宅を訪れたという虚偽の説明を行っていたことは、被控訴人の供述の信用性が乏しいことはもとより、本件事故が被控訴人の故意によるものであることを強く疑わせる事情ともいえると指摘しました。
さらに、発見時の本件車両には、車体外部全体にわたって、一定の重量があり先端が尖った金属製の道具でつけられたような傷が136ヶ所あり、車室内に大量の消火剤が散布されていたが、本件事故当時、本件駐車場内に消火器は設置されておらず、B公園内に設置された消火器が持ち去られた事実もない。本件事故が第三者によるものであるとすると、第三者は、たまたま本件駐車場に駐車されていた本件車両を見つけ、通常持ち歩くとは考えにく一定の重量があり先端の尖った金属製の道具と消火器を使って、上記のように執拗に本件車両を損傷したことになるが、その可能性は低いといわざるをえない。しかも、本件車両のドアは施錠されており、消火剤は、開いていた左後ろの窓ガラスの2~3cmの隙間から散布されたものと思われ、消火器の準備と併せて、偶然とは思われない状況が重なっている。
そして、本件車両につけられた右前輪のブレーキキャリパーにある傷の箇所にスポークが重なっており、発見時の状態では傷をつけることができないことは、上記の傷がつけられた後ホイールが回転した、すなわち本件車両が移動したことを示し、本件車両の発見時、本件車両のハンドルやシフトレバーに消火剤の粉末が付着したままで触れられた痕跡はないことは、消火剤が散布された後に本件車両が移動していないことを意味している。すなわち、何者かが本件車両外部を損傷した後、ドアを開錠しエンジンをかけて本件車両を移動させ、発見場所に駐車し、車室内の消火剤を散布したことになるが、本件車両にはイモビライザーが搭載され、発見時にはドアは施錠されていたのであるから、本件車両のキーを所持しない者が、上記のように本件車両外部そ損傷した上で、本件車両を移動させ、さらに車室内を損傷することは困難であると指摘しました。
こうして二審裁判所は、本件事故は被控訴人の故意により生じたと認められると判断しました。
【ポイント】
一審と二審で判断の分かれた事案です。
二審における控訴人の補充主張において、ETCの利用履歴から、事故当時、被控訴人の兄が勤務先のトラックを運転していたことが裏付けられ、そうすると兄が原告宅を訪問していたという被控訴人主張の根幹が崩れることになり、二審の判断に大きく影響したものと思われます。
なお、控訴審において、控訴人が、本件車両に装備されたコンピュータに記録されている車両位置情報を解析する旨の鑑定申出を行ったところ、被控訴人が、鑑定申出直後に本件車両を売却して、鑑定実施不能にしたことも「被控訴人の行動に関する被控訴人の供述について疑念を生じさせる事情である」とも認定されています。