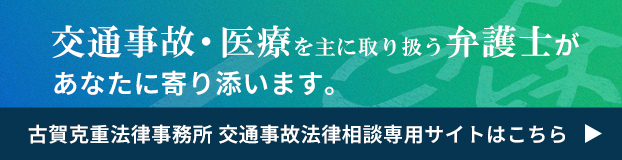和歌山地方裁判所 令和6年6月28日判決
1級遷延性意識障害等を残す17歳男子の将来介護費を日額3万円を下回ることは想定し難いと平均余命までの59年間につき日額3万円で認定した
解説
【事案の概要】
17歳男子高校生の原告は、信号のない交差点で原付自転車を運転して走行中、被告運転の普通貨物車が左方路から侵入してきて衝突し、脳挫傷、脾損傷、肺挫傷等の傷害を負い、約700日入院して症状固定し、遷延性意識障害及び四肢体幹運動障害から1級認定の後遺障害を残したため、既払金を控除し約4億円を求め、原告母は慰謝料等550万円を求めて訴えを提起しました。
裁判所は、原告の将来介護を平均余命まで日額3万円と認定しました(控訴後和解。自保ジャーナル2181号1頁)。
【裁判所の判断】
裁判所は、将来介護費について、原告は令和4年5月以降センターに入所しており、福祉費・医療費の1日当たりの総額は3万6000円を下らない。この金額は厚生労働省の定める基準に沿っているとして、相当と評価することができるし、今後見込まれる長年にわたる介護生活に要する費用として、日額3万円を下回ることは想定し難いとしました。
さらに裁判所は、逸失利益について、原告は本件事故当時満17歳の男子高校生であり、本件事故による後遺障害の症状固定は令和2年4月であるから、基礎収入は、症状固定日の属する年である令和2年の男子学歴計全年齢平均賃金545万9500円とすべきである。労働能力喪失率100%及び労働能力喪失期間49年(ライプニッツ係数18・1687)につき当事者間に争いがないから、逸失利益は9919万2017円となるとしました。
傷害慰謝料について、裁判所は、原告の入院期間が約23カ月であることを前提とした金額(338万円)に、原告は、極めて重篤な脳の傷害を抱えて長期入院を余儀なくされたとの事情など諸般の事情を考慮し、傷害慰謝料を504万4000円とするのが相当であるとしました。
なお裁判所は、原告母の慰謝料について、本件事故当時高校在籍中の17歳であった原告に、極めて重篤な後遺障害が残存したことにより、原告の将来を慮って多大な精神的苦痛を被ったといえるから、これに対する慰謝料の金額を500万円とするのが相当であると判断しました。
【ポイント】
将来介護費については、赤本で「職業付添人は実費全額、近親者付添人は1日つき8000円、但し、具体的看護の状況により増減することがある」とされています。裁判例も被害者の置かれた状況に応じて様々な判断が見られます。
札幌地方裁判所令和3年8月26日判決(自保ジャーナル2108号)は、自賠責1級1号遷延性意識障害を残す19歳男子原告の将来介護料につき、介護状況については、今後、施設入所や医療機関への入院、短期入所の利用なども否定できないこと、将来的に姉が同居する蓋然性がある等から、職業介護と近親者介護を伴せ、日額2万円で平均余命まで認定しました。
大阪地方裁判所令和2年3月31日判決(自保ジャーナル2071号)は、遷延性意識障害等から自賠責1級1号後遺障害を残す15歳男子原告の将来介護費用につき、職業介護人による介護費用を月額48万円で平均余命まで認め、両親分については日額5000円で平均余命まで認定しました。