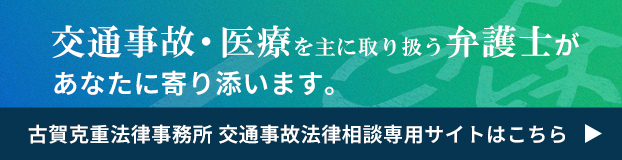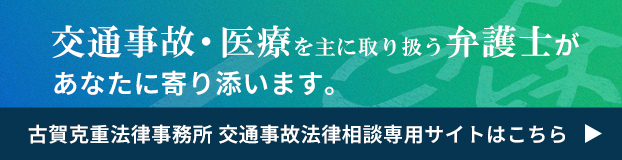東京地裁 令和7年3月31日判決
自賠責併合7級右上肢変形障害及び同併合8級胸腹部臓器障害の併合5級後遺障害を残し、減収のない公務員の労働能力喪失率を転職や退職後の職の幅が相当に狭まったと70%と認定した
解説
【事案の概要】
男子公務員(40代)は、自動二輪車で交差点を直進中、対向右折車両(中型貨物車)に衝突され、右上腕骨遠位端開放粉砕骨折、右尺骨肘頭骨折、右外傷性肺・肝臓・腎臓・副腎損傷等の傷害を負い、約350日入院含め約7年8ヶ月間通院し、自賠責8級8号右上腕骨変形障害、同12級8号右尺骨変形障害の併合7級右上肢変形障害の他、同9級11号腎臓障害、同13級11号胆嚢障害の併合8級胸腹部臓器障害から併合5級後遺障害を残しました。係争中男性死亡により相続人らが既払金約2340万円を控除し約8650万円を求めて訴えを提起しました。
東京地方裁判所は、併合5級後遺障害を残し減収のなかった男性の労働能力喪失率を70%と認め、男性の過失を1割と認定しました(確定。自保ジャーナル2196号18頁)。
【裁判所の判断】
労働能力喪失率について、後遺障害等級が併合5級であること(争いなし)を前提に、東京地方裁判所は、以下の通り詳細に検討をくわえた上で、70%と認定しました。
まず、本件事故後に担当業務が変わり、主にデスクワークを担当することで自衛官として勤務を続けることができており、その収入は事故前年のものから増収しており、そのような傾向が数年にわたって継続していることを指摘しました。そして、業務遂行状況や収入状況に加え、公務員であることなども踏まえると、男性に前記のような重い後遺障害が残存していても、男性の就労が今後も維持され、収入も維持ないし増収となる可能性が高いといえ、この点は、男性の後遺障害等級どおりの高い労働能力喪失率(注:5級79%)とすることが相当でないことの根拠となり得る事情といえると指摘しました。
その上で、まず、男性の後遺障害による業務上の具体的な支障等についてみると、男性の右上肢の後遺障害は、上腕骨及び尺骨の骨幹端部に癒合不全が生じている上、右前腕の可動域制限や右肘関節の機能障害があり、可動域は日常生活がかろうじてできる範囲であり、右肘関節痛や右肘から前腕・指先にかけての痺れ等の症状も生じている状態であって、利き手である右手でボルトを締めることすらできず、ボールペンを握ることはできるもののしっかりと字を書くこともできず、箸を使うこともできなくなったというものであり、また、右の腎臓を亡失した後遺障害については、一側の腎臓を失った場合、残った腎臓に負担がかかることによって腎機能の低下を来しやすくなるとされているところ、男性の腎機能の低下は中等度であり、中等度以下の場合には、概ね軽度の制限を行い、肉体労働を避けるべきであるとされ、実際、医師からも激しい運動は行わないよう指示を受けているとしました。さらに男性には、胆嚢を亡失するという後遺障害も生じていると指摘しました。
また、男性が本件事故当時に従事していた整備員という業務内容に加え、事故当時のように高い評価を得るに至るまでには、高度の専門的知見や技術を習得するために相当の時間と労力を費やしたものと考えられるところ、本件事故による後遺障害によって整備の業務を遂行することができなくなった上、自衛隊における他の肉体労働を要する業務に従事することも困難になったと考えられるとしました。
さらに、男性の当時の年齢に加え、男性が自衛官として長く勤務し、高度の専門的知見や技術を要する職務において高い評価を得ていたことなどからすれば、今後、階級が上がる可能性もあったものと認められるところ、本件事故による後遺障害のため、体力を要する検定において満足のいく結果を出すことが不可能となったことから昇任試験に合格することが困難となったことなども認められるとしました。
そして、男性の右上肢に係る後遺障害の内容・程度を踏まえると、デスクワークの業務に変わったとはいえ業務に支障が生じないようにするためには相当の努力が必要であることは想像に難くなく、事故後に減収がなかったことにはそのような男性の特段の努力等によるところが小さくないといえるとしました。加えて、男性が高校卒後から自衛官として働いてきたが、本件事故による後遺障害は、自衛官としてできる業務の幅を著しく限定するだけでなく自衛官として働くための様々なルールを順守することを難しくさせるものであり、自衛官として働き続けることを困難とする要因となり得るものであることろ、男性がこれまでのキャリアで得た整備員としての技術や知見が後遺障害により生かせない状態となったことなどから、転職や退職後の職の幅が相当に狭まったものと認められるとしました。
以上を踏まえると、減収がなかった点を考慮しても、男性の労働能力喪失率は70%とするのが相当であると認定したものです。
【ポイント】
事故後減収のない公務員の後遺障害逸失利益については、以下の判決があります。
福岡地裁令和5年7月13日判決(自保ジャーナル2157号)は、自賠責12級12号左足第1指関節機能障害、同14級9号腰痛、背部痛から併合12級後遺障害を残す減収のない24歳公務員の原告の後遺障害逸失利益算定につき、本件事故の後遺障害が原告にもたらす経済的不利益を是認するに足りる特段の事情があるとして、女子専門学校卒全年齢平均を基礎収入に67歳までの43年間12%の労働能力喪失で認定しました。
大阪地裁令和3年2月25日判決(自保ジャーナル2093号)は、自賠責12級7号認定の右股関節機能障害を残す事故後減収のない31歳公務員の原告の後遺障害逸失利益算定につき、今後の職務や異動の範囲が制限される可能性もあること等にも鑑みると、一定の逸失利益を認めるとして、事故前年収を基礎収入に67歳までの34年間10%の労働能力喪失で認定しました。
大阪地裁令和3年1月29日判決(自保ジャーナル2095号)は、併合12級左感音難聴等を残す減収のない30歳公務員の原告の後遺障害逸失利益算定につき、減収が生じていないとしても、現に業務に支障が生じていることが認められ、昇任昇給等の人事評価上不利益を被ることがあり得るとし、事故前年収を基礎収入に60歳までの30年間10%の労働能力喪失で認定しました。